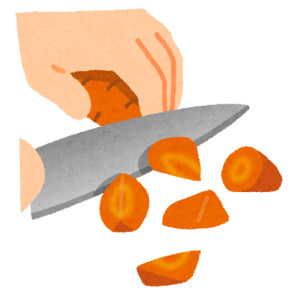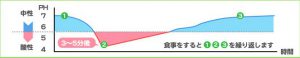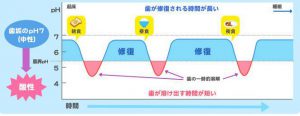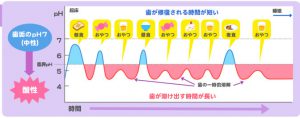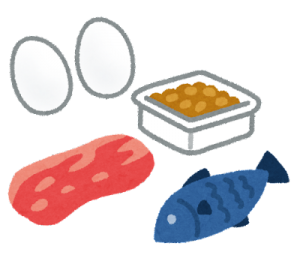全身の入り口であるお口の中に入るもの、つまり食べ物や飲み物は、生きる土台でありスタートです。
私たち「歯科で働く管理栄養士」が、歯のお話や食事、生活習慣についてなど様々なテーマで毎月ブログにてお知らせ致します。
普段の生活にお役立ていただけたら幸いです。
よろしくお願いします♪
**************************************************************************************************************
こんにちは😀歯科管理栄養士の瀬野です🦷
今回は外食、中食(調理済みの食品を購入して自宅で食べること)の際の食事の選び方についてお伝えします。仕事や家事が忙しく、毎日毎食自炊することは本当に大変かと思います😵
外食や中食はとても便利なので活用する方も多いと思いますが、特徴や選び方を意識して利用してみましょう☝️
外食や中食の特徴🍜
⑴エネルギー・脂質が多い
からあげやてんぷらなど油を使った料理が多いため、エネルギーや脂質が高くなりがちです。また、どんぶりやパスタなど主食メインの単品料理が多いためエネルギーも高くなります。
⑵塩分が多い
冷めても美味しく感じられるように塩分や甘さが強くなっています。一度濃い味付けに慣れてしまうと味に鈍感になり、どんどん濃い味を求めてしまいます。
日本人の1日の塩分目標量は男性:8g、女性7g未満です。

図を見てわかるように、うどんやラーメンには多くの塩分が含まれています。汁を全て飲み干してしまうと1日の目標量の半分以上の塩分を摂取することになるので注意が必要です。
⑶野菜が少ない
1日の野菜の摂取目標量は350g、毎食120gです。意識して心がけないと野菜不足になりがちです。120gの目安→生野菜だと両手いっぱい、茹で野菜だと片手いっぱい程度
選び方、食べ方のポイント
・エネルギー量の表示をチェックする👓栄養表示のチェックを習慣化するとエネルギーの高い食品がよく分かるようになっていきます。
・バランスをチェックする🍱主食(ご飯、パン、麺など)、主菜(肉、魚、卵、大豆製品など)、副菜(野菜、きのこ、海藻など)が揃っているか❓
・調味料を工夫する🍽付属の調味料は初めから全てかけずに味をみながら少しずつ付けてみましょう。味が物足りない時は七味やレモンなど酸味や辛味を足すと塩分も抑えられます。
・野菜を1品プラス🥕🍅🥦カット野菜を常備したり、サラダを1品増やすことで野菜不足を解消できます。ただし、ポテトサラダやマカロニサラダ、パスタサラダなどは実際に野菜の割合は少なく、炭水化物(糖質)が多く含まれているものが多いので注意が必要です🥗
外食や中食は便利ですが偏ったメニューを食べていると食生活が乱れて生活習慣病を招く原因となってしまいます。
メニューの選び方や食べ方に注意して食事を楽しみましょう😇