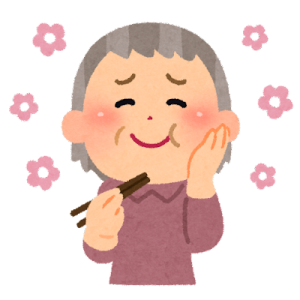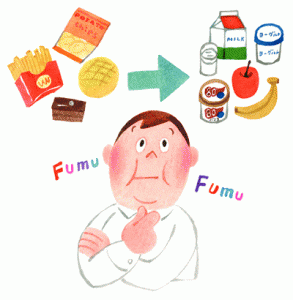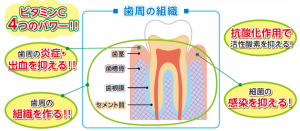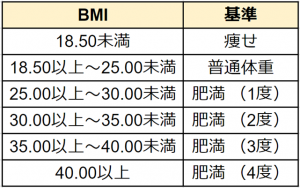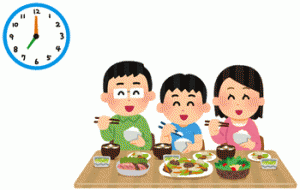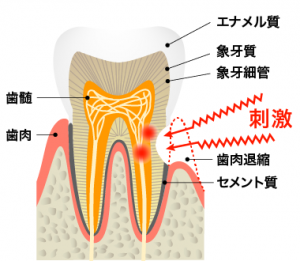全身の入り口であるお口の中に入るもの、つまり食べ物や飲み物は、生きる土台でありスタートです。
私たち「歯科で働く管理栄養士」が、歯のお話や食事、生活習慣についてなど様々なテーマで毎月ブログにてお知らせ致します。
普段の生活にお役立ていただけたら幸いです🔅
よろしくお願いします♪
*****************************************************************************************************
みなさんこんにちは。歯科管理栄養士の瀬野です☺️
「オーラルフレイル」という言葉をご存知ですか??
「フレイル」とは加齢により心身が老い衰えた状態を指し、大きく「身体的フレイル」「精神、心理的フレイル」「社会的フレイル」の3種類に分けられます。
「オーラルフレイル」とは、口腔機能が衰えた状態を指します。かむ力の低下や舌の動きの悪化が食生活に悪影響を及ぼし、身体機能の低下につながります。さらには滑舌が悪くなり、人と楽しく食事が出来なくなって閉じこもったりと、人や社会の関わりが減ってしまうことで心理的、社会的にも悪影響を及ぼすと言われています。
今回はオーラルフレイルを予防するための、食事のポイントを紹介します!
👆よく噛んで食事をする
よく噛むことで口の周りの筋肉が鍛えられます👄具体的には、、、
・お肉や野菜など、噛みごたえのある食材を取り入れる
・具材を大きめにカットする、加熱時間を短めにして歯ごたえを残す
・生野菜やナッツなど食感のあるものを食べる などです。
👆たんぱく質、エネルギーを積極的に摂取する
低栄養を防ぐためにたんぱく質とエネルギーは必須です!!
・たんぱく質・毎食たんぱく質を取り入れる
お肉やお魚など、毎食手のひら1枚分のタンパク質を摂ることが目標です。
・ヨーグルト、チーズケーキ、プリンなど間食で補うこともできます。
・市販の栄養補助食品なども活用してOK!
・バターやオリーブオイルなど、油脂類でカロリーアップ など
食べこぼしがあったり、むせやすい、口が乾燥しやすいなどの症状がある方はオーラルフレイルが始まっている可能性があります。
オーラルフレイルを予防するために、日々の食事を見直してみましょう!
口の筋肉を鍛えるトレーニングもいくつかあります!
興味がある方はスタッフに聞いてみてください😁