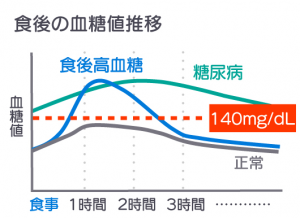全身の入り口であるお口の中に入るもの、つまり食べ物や飲み物は、生きる土台でありスタートです。
私たち「歯科で働く管理栄養士」が、歯のお話や食事、生活習慣についてなど様々なテーマで毎月ブログにてお知らせ致します。
普段の生活にお役立ていただけたら幸いです。
よろしくお願いします♪
*************************************************************************************************************
こんにちは😃
管理栄養士の花村です🌷
今回のテーマは「食物アレルギー」です。
子供から大人まで世界で幅広く見られるアレルギーです。
今日はその代替食品についてお伝えしたいと思います。
まず食物アレルギーとは、特定の食物を摂取することにより免疫システムが過敏に働き、
体に不利益な症状が現れることを言います。
原因物質は、食物に含まれるタンパク質です。
食物を摂取し腸管から成分が吸収される際に、体が特定のタンパク質を異物だと認識すると、血中のIgE抗体(免疫グロブリンE)と呼ばれるタンパク質が反応してアレルギー症状が出ます。
そのなかでも今回はアレルギーの代表的な卵・乳・小麦の代替食品についてお伝えします。
🥚卵
主な栄養素 タンパク質
➡️代替食品 肉、魚、大豆製品、乳製品
🥛乳製品
主な栄養素 カルシウム
➡️代替食品 大豆製品、魚、青菜、海藻
🌱小麦
主な栄養素 炭水化物
➡️代替食品 ごはん、雑穀、米粉や雑穀製のパンやめん、芋類
などが挙げられます。
また、食事は主食、主菜、副菜が常に揃うように心がけると栄養のバランスが整いやすくなります。
🍚主食 (ごはん、パン、めんなどの穀物、いも)
主な栄養素 炭水化物
主な役割 体を動かすエネルギー源となる
🍖主菜 (肉、魚、大豆製品、卵、乳製品)
主な栄養素 タンパク質、カルシウム
主な役割 筋肉、臓器、骨などの成分となる
🥦副菜 (野菜、海藻、果物)
主な栄養素 ビタミン、ミネラル、食物繊維
主な役割 体の機能を整える
代替食品を知って足りない栄養を補って健康な体でいましょう😘